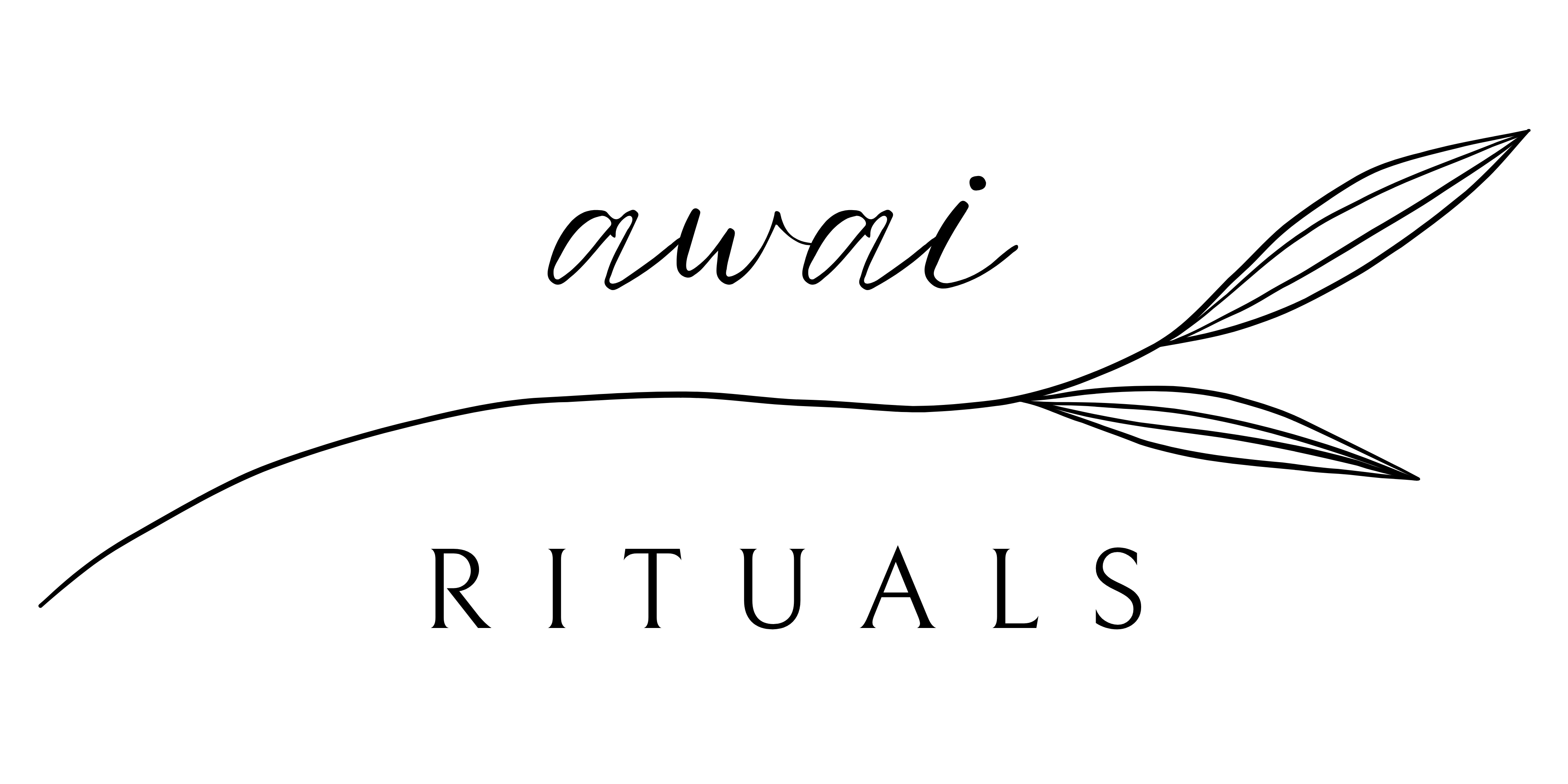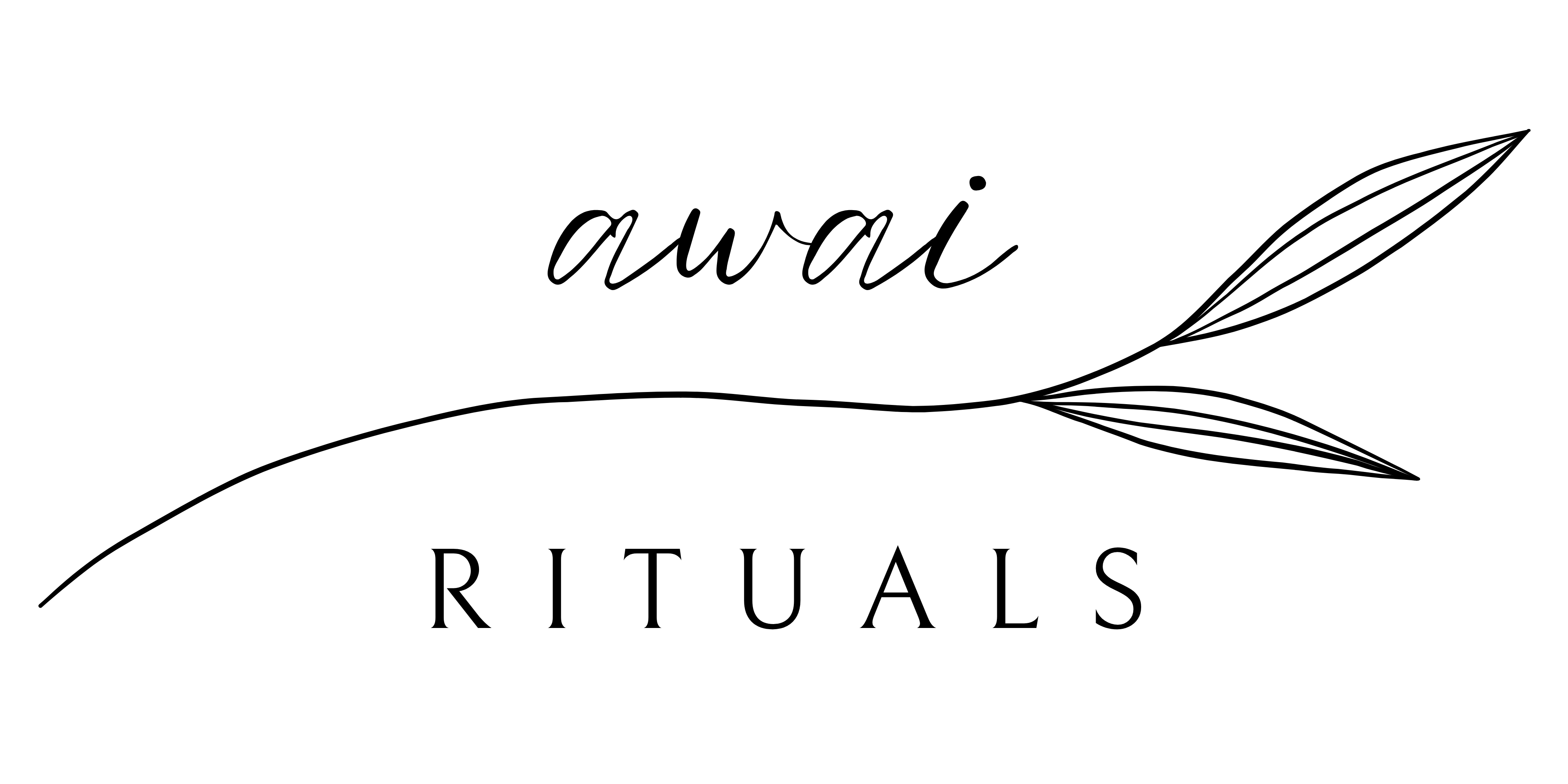2025/10/04 15:22
振り返ると、社会人になって以降、定期的に「お稽古」に通っていました。
はじめはいけばな。
月に3回、仕事帰りに教室に立ち寄り、花を活ける。
毎回、季節の花や枝が用意されており、それらを使って教科書に載っている「型」に合わせて活けていく。
基本の型に始まり、常に基本を意識しながらも少しずつ応用の幅を広げていく。
枝の伸び方や葉・花の付き方をよく見て、残す枝と切り落とす枝を決める。
活けるものたちによってできる空間を見つめる。
それは、それまでの人生で体験してきたピアノやダンスなどのレッスンとはまた少し違って、
静かにその場に立ち止まり、目の前のものとの関係を通じて自分自身を見つめるような、
そして自然と姿勢が正され、呼吸が深くなり、心が静かになるようなプロセスでした。
大学卒業後、新入社員として入社した会社での仕事や人間関係に慣れてくる中で、
知識やスキルを身につけるのとは違った、自分の全体、そして中心へ立ち戻るような時間を必要としていたのかもしれません。
その後、転職をして移り住んだ東京でも、転職先を退職し、ふらふらしているときに近くのいけばな教室に通っていました。
そのときは、肩書きもなく、明確なビジョンもない中で、
何者でもない自分として、ただ目の前のものに向き合うことに、
「存在の感覚」を見出してたのかもしれません。

その後、しばらくして今度は煎茶道のお稽古に通い始めました。
すでに日本茶の店で働いていましたが、煎茶についての知識やお手前を身につけるためというよりも
やはり、姿勢を正し、深く呼吸をし、そこにあるお茶と時間を味わって自分の中心に帰ってくるような時間として過ごしていました。
北鎌倉にあるお寺の奥の古民家が稽古の場所だったのですが、
都内からそこまで向かう道すがらすでにスピードがゆるまり、
からだもゆるまっていっていたのではと思います。
ある日、予定の電車に乗り遅れ、遅刻してしまったことがありました。
焦る気持ちがありながらも、道端に咲く小さな花を眺めながら歩き、
席に着き、深く深呼吸をして茶缶から茶葉を目分量で出し測ったところ、
そのとき必要な5gピッタリでした。
それまでの稽古を通じて、心が静まるプロセスをからだが覚えていたのでしょう。
お花を活ける、お茶を淹れる。
楽器を奏でる、声を出す。
料理をする、からだを動かす。
それらは小さなリチュアル(儀式)のようなものかもしれません。
決まった型を通じて、心やからだの状態に気づく。
「今」に気づくと、必要な変化は自ずと起こってきます。
子どもの頃のものとはまた違った「お稽古」の時間。
ぜひあなたも、役割や評価を手放して「自分」の全体を感じる時間を味わってみませんか?
・・・
awai RITUALSで開催するお茶のお稽古についてはこちら