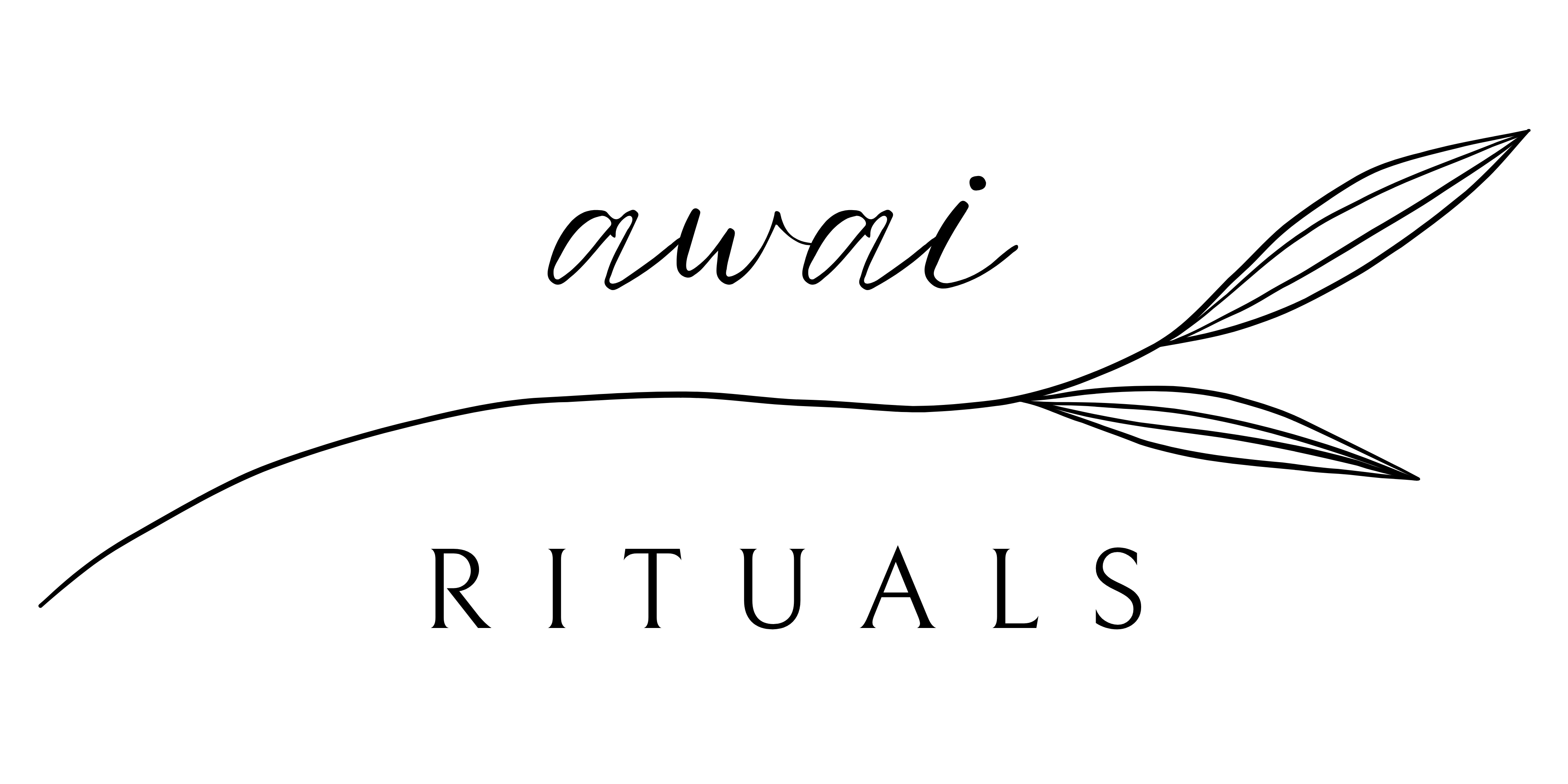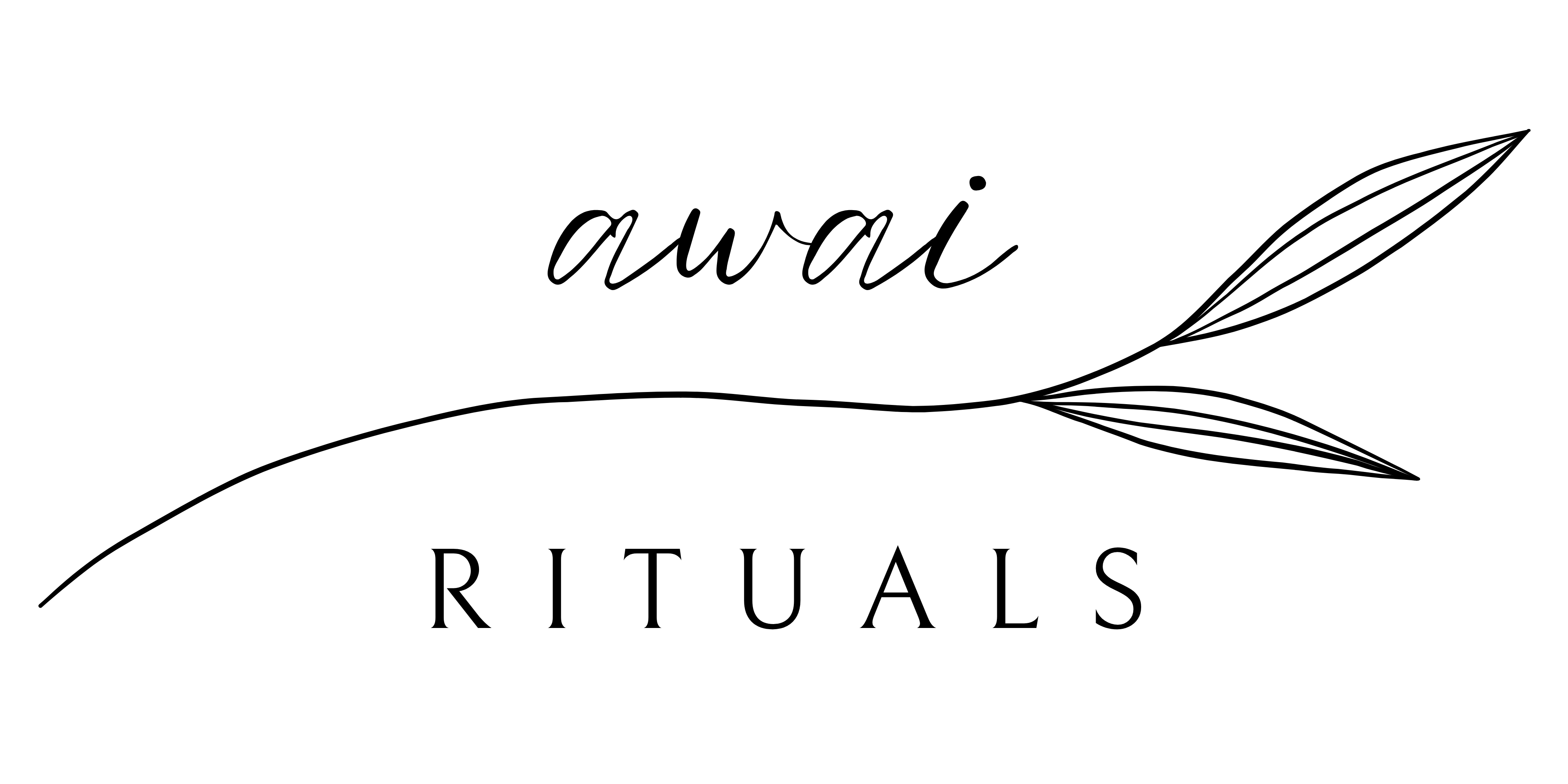2025/09/01 16:37
わたしたちがお店で手にする「完璧な」商品を作る過程で、
「完璧ではないから」とはじかれているものがあるということを知ったのは、とある場所を尋ねたときでした。
大学で知り合った友人の実家は佐賀県有田市にある200年近い歴史を持つ、有田焼の窯元。
製陶所の敷地内1800年代に作られたと言われる登り窯(のぼりがま)の跡も残っており、
友人は有田焼の歴史や製陶のプロセスを分かりやすく教えてくれました。
その中で、陶器を焼くときには登り窯の中で焼き物が歪んだり割れたりしてしまうことがあるということを知りました。
また、絵付けをしたところがどんな色になるかも焼き上がってからしか分からないため、
長い経験を積んでやっと決まった商品を同じ品質で作れるようになるということでした。
今でこそ安価でも手に入るようになりましたが、「焼き物は高い」というイメージを持っている人もきっと少なくはないでしょう。
それは、規格品として売れないものが製造過程でどうしてもできてしまうため、
流通に乗るものはその分高く価格を設定しなければならないためなのです。
「経験の浅い職人が作ったものも、『規格外品』としてではなく味わいや個性として購入してもらえるように、色ムラをデザインに取り入れている新しい商品を考えているんだ」と友人はできたばかりのサンプルを誇らしげに見せてくれました。
細やかな絵付けのものや、個性的な釉薬の表情から「一点物」として販売されるものもありますが、
日常遣いのために気軽に購入できるかというとなかなかそうではありません。
現在はガス釜を使っているところも多くありますが、それでも生地や釉薬に含まれる鉄分によって小さな黒い点ができることがあります。
ゆがみやゆらぎがあるのは天然の素材を使って、人の手が加わっているからこそなのですが
それらはデパートなどの小売店に向けた流通からはじかれてしまうのです。
わたしたちがお店で「一点物」に出会うことはあっても「小さな個性があるもの」に出会うことがないのはそんな理由からなのです。
これはきっと、焼き物に限ったことではないでしょう。
日本では1980年代後半のバブル期を経て個人や違いを尊重するような社会的な意識が高まっていったと言われていますが
市場に流通する商品はいまだ画一的なものが大半を占めています。
「どれも同じ」があまりにも当たり前すぎて、「規格外のものがはじかれている」ことにさえ気づいていないのではないでしょうか。
テレビCMに出てくる「幸せそうな家族」が知らず知らずのうちに「幸せな家族像」として刷り込まれ
そこから外れていると何か自分には足りないものがあるような気持ちになるように、
日々目にするもの、手にするものは知らず知らずのうちにわたしたちに「あるべき姿」を刷り込んでいく。
「ありのままの自分や他者を受け入れたい」と思いながらも、それが難しいと感じるのは
わたしたちの意識の中に「規格に則ったものが価値があるもの」「規格から外れると価値がない」という
強烈な価値観の植え付けがあるからかもしれません。
自然の中で生まれたものは画一的ではありません。
生き物にも植物にもそれぞれの形があり、生き方があり、一つとして同じものはない。
人が作ったものも、本来そうなのではないでしょうか。
人の息遣いがあり、リズムがあり、ときに躍動や躊躇がある。
コピー&ペーストで無限に増やせるものではない、ゆらぎのあるものを愛することが
自分自身の唯一無二のいのちを愛でることにつながるのではと、
「ちいさな個性」のある茶器たちを見ながら考えています。

awai RITUALSで販売している「あわいもの」についてはこちら